ここをクリック◆◆◆
| 6月2日(日) 続き 晴れ | ◆このページをとばすときは ここをクリック◆◆◆ |
 Babe Ruth Birthplace and Museumをとても早く見終わってしまったので、時間的にはずいぶん余裕があったはずでしたが、オーダーしたカニがなかなか出てこなかったのと、そのカニとの格闘を終え、大量の殻がテーブルの上に山と積まれた頃には、ちょうどランチの人々でレストラン内がごった返し、私たちのテーブルを担当していたウエイトレスさんが全然捕まらなくて会計が出来なかったのとで、Inner Harborのレストランを出たのは、もう試合開始30分前くらいでした。ここから、Camden Yardsまでは、じゅうぶん歩ける距離なのですけれど(地図はこちら)、午前中に通ったときとはうって変わって、いろいろな方角から試合を観戦する人々がどっと押し寄せていました。レストランのあるHarbor Placeや、その他のホテル、Convention Centerなど、Inner Harbor周辺にある建物は、Sky Walkという空中の通路で繋がっていて、これが大変便利でした。日が照り返している地上よりは、風があってずいぶん暑さがマシな上、週末のConvention Centerは人が少なく、球場への行き帰りに、冷房の効いたきれいなロビーでひと休みしたり、お手洗いを使ったりさせてもらいました。
Babe Ruth Birthplace and Museumをとても早く見終わってしまったので、時間的にはずいぶん余裕があったはずでしたが、オーダーしたカニがなかなか出てこなかったのと、そのカニとの格闘を終え、大量の殻がテーブルの上に山と積まれた頃には、ちょうどランチの人々でレストラン内がごった返し、私たちのテーブルを担当していたウエイトレスさんが全然捕まらなくて会計が出来なかったのとで、Inner Harborのレストランを出たのは、もう試合開始30分前くらいでした。ここから、Camden Yardsまでは、じゅうぶん歩ける距離なのですけれど(地図はこちら)、午前中に通ったときとはうって変わって、いろいろな方角から試合を観戦する人々がどっと押し寄せていました。レストランのあるHarbor Placeや、その他のホテル、Convention Centerなど、Inner Harbor周辺にある建物は、Sky Walkという空中の通路で繋がっていて、これが大変便利でした。日が照り返している地上よりは、風があってずいぶん暑さがマシな上、週末のConvention Centerは人が少なく、球場への行き帰りに、冷房の効いたきれいなロビーでひと休みしたり、お手洗いを使ったりさせてもらいました。
 そして、大勢のファンに混じって、いちばん手近の入口から入場。とりあえず、かなりよい席のはずなので、ネット裏に近いに違いないと、外野をぐるりと回って、グラウンドが正面に見えるところまで歩いてみました。でも、私たちの席のエリアを示すサインがどこにもないのはなぜ??係員の人に聞いてみたら、その席は位置的に外野にとても近い2階席で、値段が高いのは、きれいなラウンジを使えたり、座席で食べ物を注文したりできるためだったのでした・・・ちょっと失敗。事前にチケットを買うときに、ちゃんと球場の座席図を確認するべきでしたね。ペットボトルの持ち込みは出来ないと思った(実際はOKでした。)ので、球場内の売店で水を買ったり、あれやこれやで、座席にたどり着いたのは、ほとんど試合が始まる直前になってしまいました。
そして、大勢のファンに混じって、いちばん手近の入口から入場。とりあえず、かなりよい席のはずなので、ネット裏に近いに違いないと、外野をぐるりと回って、グラウンドが正面に見えるところまで歩いてみました。でも、私たちの席のエリアを示すサインがどこにもないのはなぜ??係員の人に聞いてみたら、その席は位置的に外野にとても近い2階席で、値段が高いのは、きれいなラウンジを使えたり、座席で食べ物を注文したりできるためだったのでした・・・ちょっと失敗。事前にチケットを買うときに、ちゃんと球場の座席図を確認するべきでしたね。ペットボトルの持ち込みは出来ないと思った(実際はOKでした。)ので、球場内の売店で水を買ったり、あれやこれやで、座席にたどり着いたのは、ほとんど試合が始まる直前になってしまいました。 1番を打つことが多いイチローは、遠征先であれば、試合でいちばん最初に打席に立ちます。急がなくちゃ・・・と思ったら、今日の打順は、クリーンナップの一角である3番。しかも、指名打者なので打つ方専門で、守備にはつきません。せっかく楽しみにしていたのに、プレーを見るチャンスが半減してしまったのは、ちょっと残念。でも、こんなに暑い日のデーゲームだから、まあ、主力選手なら休養を取っている場合もありえるわけで、それを考えれば、まだこれでもよかったのでした。そして、第1打席で、早速、巧打のヒット!相手チームのはずなのに、球場内がドッと湧いたのにはちょっとびっくりしました。New Yorkの試合では、いくら、イチローが人気選手だからって、ヒットに喜ぶのは一部だけ。かえって相手チームにとってイヤな活躍する選手ほど、ブーイングが多かったりします。なのに、この反応はちょっと意外でした。
1番を打つことが多いイチローは、遠征先であれば、試合でいちばん最初に打席に立ちます。急がなくちゃ・・・と思ったら、今日の打順は、クリーンナップの一角である3番。しかも、指名打者なので打つ方専門で、守備にはつきません。せっかく楽しみにしていたのに、プレーを見るチャンスが半減してしまったのは、ちょっと残念。でも、こんなに暑い日のデーゲームだから、まあ、主力選手なら休養を取っている場合もありえるわけで、それを考えれば、まだこれでもよかったのでした。そして、第1打席で、早速、巧打のヒット!相手チームのはずなのに、球場内がドッと湧いたのにはちょっとびっくりしました。New Yorkの試合では、いくら、イチローが人気選手だからって、ヒットに喜ぶのは一部だけ。かえって相手チームにとってイヤな活躍する選手ほど、ブーイングが多かったりします。なのに、この反応はちょっと意外でした。
試合の方は、Settle Marinersの先発投手、Pineiroが不調だったのか、Baltimore Oriolesのバッティングの調子が異常によかったのか、初回からOriolesが打ちまくり、気づいたら、まだ2回を終わったばかりなのに、6 - 0と大量リード。チーム力的には、アメリカン・リーグ西地区の首位を独走するMarinersと、東地区3位とはいっても、上位2チームに大きく水を開けられているOriolesとを比べれば、圧倒的にMariners。とはいっても、序盤でこれじゃあ、今日はちょっと勝ちはムリかな・・・というムードだったので、私はイチローの打席以外はゲームにあんまり注目せず、上から見下ろせる観客席であることを利用して、球場にいるファンのウォッチングを始めてしまいました。
ここで、まとめて公開!Camden YardsのファンのTシャツ・ウォッチング。
  | パターン1:地元チーム 普通、どう考えても、本拠地のチームの選手のTシャツを着るのが一般的です。OriolesのTシャツを着た人はやっぱり多く、その中で圧倒的に目立ったのは、午前中にもその功績をたくさん見てきたCal Ripken Jr.のもの。いろいろなパターンのTシャツがありましたけれども、かなりの確率で、皆、8の番号のTシャツを着ていました。いくら人気選手だからって、引退してしまった選手が、まだいちばん人気があるというのは、ある意味では、その後のチームのスター不在を如実に表しているともいえるのでしょう。 |
パターン2:対戦チーム そして、対戦相手であるMarinersを応援しに来る人たちもいます。この中では圧倒的にイチロー!ただ、これもNew Yorkでの試合とは大きく違うのが、Tシャツは着ていなくても、Marinersのキャップをかぶったりした人の数がとっても多いということ。右の写真の男の子の前の座席の子もMarinersのキャップをかぶっています。私たちの席の後ろの列に座っていた若者のグループも、なぜか、みんなでMarinersを応援していたし、本拠地が近いチームならまだしも、西海岸のチームの応援をするファンが、東海岸のこの球場で、なんでこんなにたくさにるのか、かなり不思議でした。 | 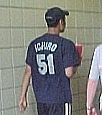 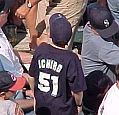 |
| パターン3:?????? そして、もっとずーっと不思議だったのが、今日の試合に関係ない選手のTシャツを着ている人たちがたくさんいたこと!Yankeesのプリンス、Derek Jeterは、やっぱり人気なんですね。(写真:上段)まあ、ここで試合もしょっちゅうあるし、違うところに住んでいても、常勝Yankeesなら、まだ応援のしがいがあるから、あんまり見たことはないけれど、百歩譲って、そういう人がいてもおかしくはないのかもしれません。 でも、これはさらに不可解な、Barry Bondsのユニフォームにキャップをかぶった黒人の女の子。一緒にいたボーイフレンドは、まったく普通の格好だったので、彼女が熱烈なBondsファンなのかも?しれません。でも、じゃあ、なんで今日の試合見に来たんでしょう???(写真:下左) さらに、これはもっとよくわからない、Michael JordanのTシャツを着た人。彼が先シーズン、突然、Washington Wizardsで現役復帰をしたのは、皆さんご存じの通りです。確かに、BaltimoreとWashington D.C.は、車で1時間程度の近距離。それにしても、あれはバスケットで、スポーツすら違うってば・・・(写真:下右) |

 あと、結構面白かったのが、Oriolesのマスコット、通称Bird君。どこの球場にもいる、着ぐるみなのですけれど、その名前通り、動きがとってもよく、チャンスやピンチになると、観客席のどこかに現れ、皆に応援をうながします。黒とオレンジという、ものすごく目立つ色合いということもありますが、とにかく、外野、内野、果ては放送席まで、至るところに出没していました。それとも、もしかしたら、この着ぐるみって、何人もいたりするのかしらん? チャンスになると、スコアボードの画面にまで登場し、ガランとした部屋みたいなところで、このBird君が手拍子をしている様子が大写しになるのは、ちょっとだけ不気味でした。
あと、結構面白かったのが、Oriolesのマスコット、通称Bird君。どこの球場にもいる、着ぐるみなのですけれど、その名前通り、動きがとってもよく、チャンスやピンチになると、観客席のどこかに現れ、皆に応援をうながします。黒とオレンジという、ものすごく目立つ色合いということもありますが、とにかく、外野、内野、果ては放送席まで、至るところに出没していました。それとも、もしかしたら、この着ぐるみって、何人もいたりするのかしらん? チャンスになると、スコアボードの画面にまで登場し、ガランとした部屋みたいなところで、このBird君が手拍子をしている様子が大写しになるのは、ちょっとだけ不気味でした。 試合そっちのけで、こんな写真を撮っている間も、イチローは、次々とヒットを放ち、ついには、お得意のバント・ヒットまで決めてしまい、場内はやんやの喝采。Oriolesの楽勝かと思えた試合展開も、Marinersがじわりじわりと得点し、ついには、7 - 7の同点になってしまいました。うーん、恐るべしMariners打線。となると、追うものの方が強く、8回には、去年のリーグ打点王ながら、今シーズンはいまひとつ調子が出ない主砲Bred Booneが、なんと満塁ホームランを放ってしまい、一気に11 - 7に。序盤の展開からは想像できないような、すごい逆転劇が演じられたのでした。
試合そっちのけで、こんな写真を撮っている間も、イチローは、次々とヒットを放ち、ついには、お得意のバント・ヒットまで決めてしまい、場内はやんやの喝采。Oriolesの楽勝かと思えた試合展開も、Marinersがじわりじわりと得点し、ついには、7 - 7の同点になってしまいました。うーん、恐るべしMariners打線。となると、追うものの方が強く、8回には、去年のリーグ打点王ながら、今シーズンはいまひとつ調子が出ない主砲Bred Booneが、なんと満塁ホームランを放ってしまい、一気に11 - 7に。序盤の展開からは想像できないような、すごい逆転劇が演じられたのでした。 ずっとリードされていましたし、今度は、一気に点を取ってしまったため、今日は、リリーフの長谷川・佐々木両投手の出番はなし。佐々木投手は、一応、万が一に備えて、ブルペンで投球練習はしていましたが、他の中継ぎ陣が、反撃も1点に押さえ、逃げ切ってしまいました。
ずっとリードされていましたし、今度は、一気に点を取ってしまったため、今日は、リリーフの長谷川・佐々木両投手の出番はなし。佐々木投手は、一応、万が一に備えて、ブルペンで投球練習はしていましたが、他の中継ぎ陣が、反撃も1点に押さえ、逃げ切ってしまいました。
それにしても、Marinersファンにとっては笑いが止まらないような快心の、そして、Oriolesファンにとっては、信じられない悪夢のような試合でした。私たちのお隣のご夫婦は、暑さに耐え兼ねて、中盤で席を立ってしまったのですが、きっと、彼らはOriolesが負けたなんて、夢にも思っていないことでしょう。
 ちゃんと日焼け止めを塗っていましたが、3時間少々で、すっかり日焼けしてしまったこの試合、でも、見たかいがありました!しかも、Baltimoreの野球ファンは、上のTシャツを見ていただいてもおわかりの通り、New Yorkと比べるとあんまりこだわりがない感じなので、相手チームでも全く気兼ねなく応援できてよかったです。たった3日間だけでしたけれど、カニも食べたし、美術館にも行ったし、なにより、ずっとお天気がよくて、初夏のBaltimoreを満喫することができました。この街は、きっとこれから夏にかけてが、いちばんよいシーズンなのでしょうね。今回で、Inner Harborの観光はだいたいしてしまったつもりですが、これに味をしめて、来年も、もし、夏にこのカードがあったら、カニも食べられるし、イチローを応援しに来ちゃおうかな・・・
ちゃんと日焼け止めを塗っていましたが、3時間少々で、すっかり日焼けしてしまったこの試合、でも、見たかいがありました!しかも、Baltimoreの野球ファンは、上のTシャツを見ていただいてもおわかりの通り、New Yorkと比べるとあんまりこだわりがない感じなので、相手チームでも全く気兼ねなく応援できてよかったです。たった3日間だけでしたけれど、カニも食べたし、美術館にも行ったし、なにより、ずっとお天気がよくて、初夏のBaltimoreを満喫することができました。この街は、きっとこれから夏にかけてが、いちばんよいシーズンなのでしょうね。今回で、Inner Harborの観光はだいたいしてしまったつもりですが、これに味をしめて、来年も、もし、夏にこのカードがあったら、カニも食べられるし、イチローを応援しに来ちゃおうかな・・・
| Baltimore | ||||
|---|---|---|---|---|
| 5月31日 | 6月1日 前 編 | 6月1日 後 編 | 6月2日 前 編 | 6月2日 後 編 |